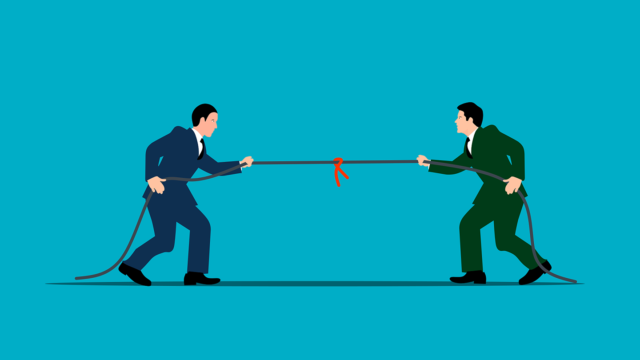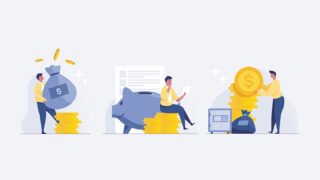見積額はバラバラでもOK|フリーランス必見!クライアント別に価格が変わる納得の理由とは?

「同じ内容のホームページなのに、クライアントごとに見積が違っていいの?」――そんな疑問を抱えたまま、見積提出の手が止まったことはありませんか?
頭では「案件ごとに事情が違う」とわかっていても、いざ説明するとなると、言葉に詰まるときってありますよね。
実はこの“価格の違い問題”、ちゃんとした理由と伝え方さえ押さえれば、何もおかしくないんです。今回は、そんな「見積額が変わる理由と、その考え方」について、フリーランスWebデザイナー歴15年の実体験をもとに、リアルに解説していきます。
「モヤモヤしながら見積書を出してる…」という方は、きっとヒントが見つかるはずです。
- フリーランスWebデザイナーとして、見積もりの出し方に悩んでいる方
- 同じ制作内容でも価格に差が出ることに不安を感じている方
- クライアント対応や価格交渉で「これでいいのか」とモヤモヤしている方
- 安定したフリーランス活動を続けたいと考えている初〜中級の方
見積はクライアントごとに変わってOK!
一見、同じ仕様のホームページだと、制作費も同じになると思われがちです。たしかに「制作そのもの」にかかる基本料金は共通かもしれません。
しかし実際には、クライアントごとに金額が異なることは普通にあります。それは、実制作「以外」に、以下のような要素が影響するからですね。
- 打ち合わせやクライアント対応にかかる時間・工数
- クライアントごとに、案件の進行具合や、トラブル対応などのリスクが異なる
- 継続案件か初回案件かによる価格の違い(要はディスカウント対応)
このように、制作以外にかかるサポート対応やリスク管理のコストも、見積にしっかり反映させるべき要素です。
結果として、クライアントごとに見積金額が異なるのは、自然なことだと言えるでしょう。
見積額が変わる5つの具体的な要因
もう少し詳しくみていきましょう。
- クライアント対応にかかる手間や時間の違い
- トラブル回避のためのリスクヘッジ料金
- 初回割引やキャンペーンで価格が変わることも
- クライアントによって”価格”の感じ方は大きく異なる
- クライアントや案件毎の”納期事情”は変わるもの
①クライアント対応にかかる手間や時間の違い
改めてお伝えすると、クライアントとのやり取りの頻度や対応にかかる時間次第で、見積額は大きく変動することはよくあります。
わたしの場合、たとえば以下のような案件やクライアントだと、制作費とは別の「追加料金」相当を上乗せることもあります。
- 訪問やオンラインでの頻繁な打ち合わせが発生する
- 毎週の定例ミーティングへの参加が必須
- サイト公開後に、CMSの操作方法を何度もレクチャー(サポート)する必要あり
- 納品後も、継続的に細かな修正対応が続く
すべての対応を制作料金に含めて、一律価格で受ける方もいるかもしれません。「クライアントに喜んでもらいたい」という気持ちは大切ですもんね。
でも、過剰なサービス提供は、自分の時間や労力を消耗し、結果的にフリーランスを長く続けていくことが難しくなるリスクもあります。
大切なのは、自分のリソースを正しく把握し、それに見合った価格設定をすること。無理のない形で仕事を続けていくためにも、「どこまで対応するか」の線引きと価格への反映は欠かせません。


②トラブル回避のためのリスクヘッジ料金
わたしは経験上、「!?これは何かトラブルが起きるかも!」と感じたクライアントに対しては、あらかじめリスクを見込んだ上で見積金額を提示することがあります。
トラブルとは、たとえば以下のようなケースが該当します。
- クライアントとの連絡が頻繁に途切れたり、音信不通になるリスクがある場合
- 情報共有にミスや漏れが多く、二度手間・三度手間の対応が発生しそうな場合
- 追加要望や修正依頼が過剰になり、当初の要件から仕様が大幅に変更するリスクがある場合
こうした兆候があれば、リスク分を上乗せしておくと安全です。
とはいえ、特に独立直後だと、事前にすべてのリスクを見抜くのは難しいですね。また、新規のクライアントや初めて関わる案件では、予測できないことも多く、慎重に進めたくても限界があります。
だからこそ、案件ごとに少しずつ経験を積みながら、意識的に「リスクを察知する感覚」を磨いていくことも、フリーランスとして長く安定して働き続けるための重要なスキルになります。
③初回割引やキャンペーンで価格が変わることも
同じホームページの制作内容であっても、「初回限定割引」や「キャンペーン」などにより価格が変わることはよくあります。
- A社:初めてのご依頼なので初回割引を適用
- B社:2回目の依頼のため通常価格で提供
特にフリーランスを始めたばかりの頃は、実績づくりや継続契約のきっかけとして、戦略的に価格を下げるケースも少なくありません。
ただし、ここで大切なのが、「通常価格」と「割引価格」の線引きを明確にしておくこと。割引を続けたままなんでも対応してしまうと、仕事量は増えても利益が出ない…という悪循環に陥るリスクがあります。
あくまで期間限定や初回限定など、条件を明確にしたうえで提供することが、持続可能な価格戦略につながります。
④クライアントによって”価格”の感じ方は大きく異なる
たとえば、ランディングページの制作費用を10万円で見積もる場合、クライアントによってその受け取り方はまったく違います。
- A社:「えっ、ソレ、高すぎない?…」
- B社:「え??そんなに安くていいんですか???」
ほぼ同じようなページ制作であっても、本当に反応が違います(笑)
当然、クライアントの立場や予算の違いなどが関係していることもあるでしょう。
いずれにせよ、「誰に、どこまで、どのように」提供するかによって、価格は大きく変わるのが現実です。見積金額には絶対的な「正解」は存在しません。
だからこそ、相手のニーズや信頼関係、プロジェクトの状況を見極めながら柔軟に価格を調整するることも、フリーランスにとって大事なお仕事になるわけですね。
⑤クライアントや案件毎の”納期事情”は変わるもの
クライアントごと、そして案件ごとに「納期」は本当にバラバラです。
たとえば、通常は1ヶ月かけて10万円で制作するホームページがあるとして。「これ、1週間で欲しいんですけど!」なんて言われたら、どう対応しますか?
素直に断るのもアリですが(笑)、場合によってはこう答えることもあります。
「1週間で対応します。ただし、リソースを最優先で割くので、料金は10万円です」――と。
緊急対応などの場面においては、スケジュールの圧迫度によって見積金額が変わることはありますよね。
フリーランスにとって、時間は最も大切な資源。だからこそ、納期がタイトな案件には、きちんと対価をのせて対応することが大切です。
大切なのは、柔軟に対応できる力を持つこと!
誤解のないようにお伝えしたいのですが、ここで言いたいのは「クライアントの足元を見て商売する」ということではありません。
状況に応じて、柔軟に価格を調整することが大事だと言いたいのです。
- 付加価値のある提案やサービスを含む場合は、価格が上がるのは当然
- 作業量が当初より増えた場合は、見積金額も再調整が必要
- クライアント側がスムーズに協力してくれる場合は、コストを抑えられることもある
自分の時間・労力・リスクを適正に見積もりへ反映させることは、プロとして当然のスタンスだと言えます。
また、いつもお世話になっているクライアントから「今回は予算が厳しいのですが…」と相談された場合、信頼関係が築けていれば柔軟に値引きに応じる選択肢もアリでしょう。
わたしは、状況に合わせて柔軟に立ち回ることこそ、フリーランスとして長く活動していくために、欠かせないスキルだと実感しています。
【まとめ】見積に差があっても「根拠」があればOK
「同じ内容なのに見積金額が違っていいの?」と不安に思うかもしれませんが、価格が変わるのには必ず理由があります。
- 打ち合わせやサポートにかかる工数の違い
- リスクやトラブルの発生リスク
- クライアントとの信頼関係・これまでの付き合い
- 提供する価値や付加サービスの有無
- 納期事情は千差万別
こうした要素を踏まえて総合的に判断すれば、クライアントごとに見積が異なるのはごく自然なことです。
大切なのは、「なぜこの価格なのか?」をきちんと説明できる軸を持っておくこと。
その理由を自分の言葉で伝えられれば、あなたの見積もりは単なる数字ではなく、信頼を生む“プロの提案”になりますよ🤗