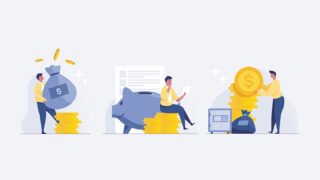フリーランスWebデザイナー必見!保守契約のメリットと判断ポイント

Webサイトは公開して終わり…ではありません。更新や修正、サーバー・ドメイントラブルなど、公開後にも対応が必要になる場面は必ず出てきます。
そこで悩むのが「保守契約はどうするか?」という問題。月額収入が増えるメリットがある一方で、制作と並行するとスケジュールが崩れたり、自由に動けなくなるリスクもあります。
本記事では、現役フリーランスWebデザイナーである筆者の実体験を踏まえ、“保守契約の判断基準”を3つに絞って解説します。
- 保守契約を結ぶべきか迷っているフリーランスWebデザイナー
- 制作業務と保守業務の両立が難しいと感じている方
- クライアントとの契約条件や金額設定に悩んでいる方
- 保守契約によるトラブルや負担増を避けたい方
“やるべき案件”と”避けるべき案件”を見極めよう
保守前提の制作案件なら基本的にやるべきですが、そうでなければ必須ではないと考えます。
クライアントとの関係性や契約経路、更新頻度を踏まえ、報酬と負担のバランスが自分の働き方に合うかを判断しましょう。
安定収入になる一方、負担が大きければ本末転倒です。無理なく続けられる契約だけを選ぶのが賢い選択です。
保守契約を判断する3つのポイント
- 制作業務と保守とのバランス
- 金額と作業負担のバランス
- 契約経路
①制作業務と保守とのバランス
制作と保守を同時に回すのって意外とハードです…。デザインやコーディングに集中したいのに、サーバートラブルや更新依頼で半日消えることもあります。特に、納期前は小さな修正でも作業の流れが大きく乱れます。
両立のコツは、保守対応の緊急度に応じた優先順位付けと、作業時間の事前ブロック。制作に支障が出るほど保守案件を抱えると、クオリティも信頼も落ちかねません。
制作クオリティを守ることが最優先なら、あえて保守契約を結ばない選択もアリです。安定収入よりも、自分のペースや仕事の質を優先することで、結果的に長く信頼を得られるフリーランスになれます。
②金額と作業負担のバランス
保守契約で大事なのは「金額」と「実際の工数」のバランスです。月額が高くても、対応内容が重く時間を奪うなら割に合いません。逆に低額で頻繁な作業依頼があれば、時間単価は大きく下がります。
「この金額ならこの範囲まで」と自分の基準を持っておき、そこから外れる依頼は交渉か辞退を検討しましょう。
フリーランスは自由に立ち回れる時間が命。その時間を守るためにも、報酬と負担の釣り合いを冷静に見極めることが必要です。
③契約経路
保守契約を決めるときは、「直契約」か「制作会社等経由」かも重要な判断基準です。
直契約なら提案や判断が通りやすく、保守範囲や料金も柔軟に決めやすいのが魅力。一方、制作会社等経由だと会社の利益分が上乗せされ割高になりやすく、承認フローやルールも複雑で対応が遅れがちです。
契約前に経路ごとの特徴を把握し、自分が動きやすい形を選びましょう。
保守契約は「金額」だけでなく、「働きやすさ」も含めて総合的に判断することが、長く続けるコツです。
わたしのおすすめ方針
- 直契約案件 → 基本は月額保守契約(更新頻度やサイト規模に合わせてプラン設定)
- 制作会社等経由案件 → 基本はスポット対応。保守を結ぶ場合は条件を厳密に書面化
- 更新頻度が低いサイト → 年間スポット契約やチケット制など、クライアントにも負担が少ない形
直契約案件
直契約は、金額交渉や作業内容の調整がしやすく、長期的な信頼関係を築きやすいのが魅力です。特に更新頻度が高いサイトや継続的な運営サポートが必要な案件は、月額制での保守契約がおすすめ。
「軽微な修正は月●回まで無料」「月1回のバックアップ+セキュリティチェック込み」など、内容をパッケージ化すれば提案もしやすくなります。
契約後も自分の判断で改善提案ができるため、保守をきっかけに追加案件へつながる可能性も高まります。
制作会社等経由案件
制作会社等経由の場合、利益が上乗せされやすく、さらに方針や承認フローが複雑なため、月額保守は割に合わないケースが多め。基本はスポット対応をおすすめします。
どうしても保守契約を結ぶなら、「対応範囲」「対応時間」「金額」「納期目安」を契約書やメールで明確化するのが必須です。
たとえば「緊急対応は別料金」「作業は営業日●日以内に完了」など具体的に記載しておけば、トラブル回避にもつながります。
更新頻度が低いサイト
年に数回しか更新しないコーポレートサイトやLPは、毎月の保守契約ではクライアント負担が大きくなりがち。そんな場合は「年間契約」や「作業チケット制」がおすすめです。
たとえば「年間5回まで修正可能」「10時間分の作業チケットを先払い」などにすれば、クライアントはコストを抑えつつ必要なタイミングで依頼可能。
こちらもスケジュール調整がしやすく、制作業務との両立にも向いています。
保守契約を結ぶときのチェックポイント
保守契約を結ぶなら、「対応範囲」「対応頻度」「料金」を必ず明文化しましょう。ここをあいまいにすると、「ちょっとだけだから…」と追加作業が増えたり、トラブル時にクライアントと制作会社の間で板挟みになるリスクが高まります。
例えば「軽微な修正」の定義を決めていなかったせいで、大規模改修まで引き受ける羽目になったり、納期トラブルで責任の所在があいまいになることも…。契約書やメールで事前に範囲・頻度・金額を共有しておけば、認識のズレを防ぎ、無駄な消耗や関係悪化も回避できます。
保守契約は、条件をクリアにすることが最大のリスク回避策です。
【まとめ】
保守契約は安定収入の柱になる一方で、作業負担や自由度の低下もつきものです。
判断の基準は「制作と保守の両立」「報酬と負担のバランス」「契約経路」の3つ。この条件をクリアできる案件だけに絞れば、制作クオリティと信頼を守りながら収入を安定化できます。
全部の案件で保守を抱える必要はありません。自分の時間とペースを大事にできる契約だけを選び、フリーランスとしての自由さと長く続けられる働き方を両立させましょう。