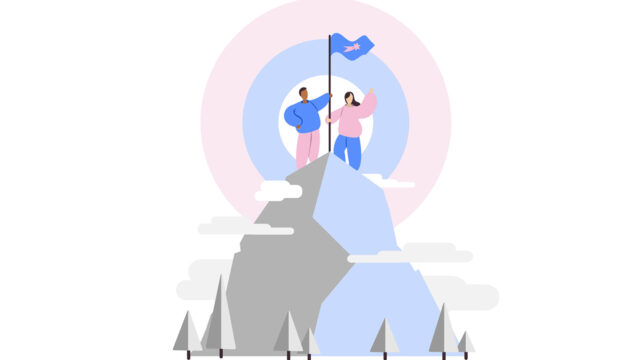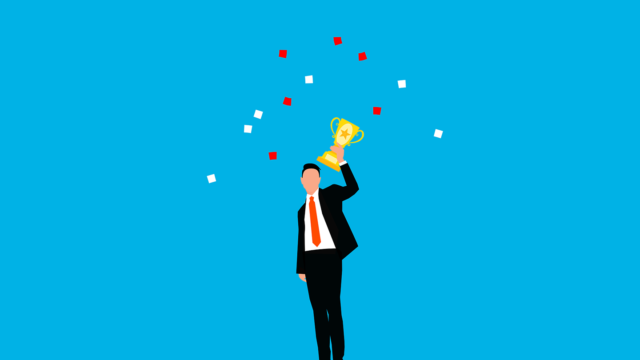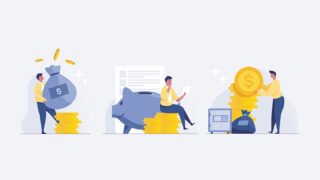もう価格設定に悩まない!フリーランスWebデザイナーの見積もり完全マニュアル

「この金額で合ってる?」と、いつも不安になるあなたへ
ホームページの制作費、どうやって決めていますか?
「周りの相場をなんとなく参考に…」「とりあえず感覚で…」——そんなふうに見積もりを出している人、実はけっこう多いんです。でもその裏で、「この価格でいいのかな…」「損してる気がする…」と、毎回モヤモヤしていませんか?
わたしも駆け出しの頃、金額を聞かれて「とりあえず◯万円で…」と出したものの、後から冷や汗…なんてことが何度もありました。
この記事では、そんな迷いを抱えるフリーランスWebデザイナーの方に向けて、“根拠のある価格”をどう作るか?を、実例ベースでわかりやすく解説します。
「もう見積もりで悩みたくない…」と思っているなら、きっとヒントになるはずです!
- 見積を出すたびに「この金額でいいのかな…」と不安になるフリーランスWebデザイナー
- 案件ごとの価格設定に毎回迷ってしまう方
- クライアントへの金額の説明に自信が持てない方
- 工数・明細・パッケージなど、見積スタイルの使い分けを知りたい方
フリーランスの制作費はこう決める!見積の基本3パターン
まずは、フリーランスWebデザイナーが制作費を決める際に使える、代表的な見積パターンを3つご紹介します。
- 工数ベースで料金を算出する
- 作業内容ごとに価格を設定する
- 固定料金(パッケージ価格)
①工数ベースで計算する
もっともオーソドックスな方法が、工数計算です。
とくにWebデザイナーなどのクリエイティブ職では、日単価または時間単価を基準に計算することが多いかと思います。
- 日単価ベースの例
1日の作業単価を50,000円と設定し、5日間の作業が必要な場合:
50,000円 × 5日 = 250,000円 - 時間単価ベースの例
1時間あたり5,000円で、2時間の作業であれば:
5,000円 × 2時間 = 10,000円
このように、「自分の単価」をあらかじめ決めておけば、作業日数や作業時間をかけるだけで見積がシンプルに計算できるのが、工数計算の大きなメリットです。
案件の規模や作業内容によって、日単位で出すか、時間単位で出すかを柔軟に使い分けられる点もフリーランスにとっては非常に実用的です。
| メリット | 注意点 |
|---|---|
| • 作業量や変更内容に応じて柔軟に金額調整できる • 追加作業や納期変更にもスムーズに対応できる |
• ヒアリングや要件定義が曖昧だと「本当にそんなにかかるの?」と疑われることも • 各工程にかかる時間をある程度“見積もる力”が求められる |
②作業内容ごとに価格を設定する
次に、作業項目ごとに個別に料金を設定する方法です。
以下の例をみてみましょう。
| 項目 | 単価 |
|---|---|
| サイト設計 | 50,000円 |
| TOPページデザイン | 50,000円 |
| 下層ページデザイン(1Pあたり) | 10,000円 |
| コーディング(1Pあたり) | 10,000円 |
| WordPress初期設定 | 50,000円 |
| マニュアル作成 | 15,000円 |
あらかじめ「設計」「デザイン」「コーディング」などの工程ごとに料金を設定しておくことで、見積が出しやすくなります。
工数計算に慣れていない方や、作業工程があらかじめ明確に決まっている場合におすすめです。
| メリット | 注意点 |
|---|---|
| • クライアントにとって見積の内訳がわかりやすい • 追加作業・修正対応に柔軟に対応しやすい |
• 見積外の作業が発生した場合は要注意。その場合はどうするかを契約時に決めておこう。 • 想定外の修正や工数増加に備えて、バッファーや追加料金の設定を! |
③固定料金(パッケージ価格)
あらかじめ提供するサービスの内容と金額をセットにして提示するやり方です。
内容と価格が明確に決まっているため、クライアントにとっても分かりやすく、検討しやすいのが特徴です。
- LP制作(最大10,000px):●●●●円
- ホームページ制作(5ページまで):●●●●円
- WordPressサイト制作一式:●●●●円
このようなパッケージは、すでに関係性が築けているクライアントや、「前と同じ内容でお願いしたい」といったリピート案件に特に向いています。
| メリット | 注意点 |
|---|---|
| • なんと言っても分かりやすい • 見積作業の時短&効率化ができる |
• やり取りに慣れていないクライアントや、初めて取り組むような案件には不向き • 仕様変更が多い案件には不向き |
見積方法は1つに絞らなくてOK!柔軟に使い分けよう
見積の出し方に「これが正解」はありません。
わたし自身、フリーランスのWebデザイナーとして15年以上活動していますが、クライアントや案件の内容によって柔軟に使い分けています。
- 工数ベースで詳細に見積もる
- クライアントや案件ごとに固定価格を設定する
- パッケージ商品として価格を提示する
はじめのうちは「どの見積方法でやればいいのか分からない…」と悩むこともあるかもしれません。ですが、実務を重ねるうちに、少しずつ判断力や価格設定の感覚が身についてきます。
たとえば、
「この案件は仕様変更が多そうだから、作業明細ベースで見積を出して、バッファを含めておこう」
こんな具合に、案件の特性に合わせたムリのない価格設定ができます。
自分で自分の首を絞めることも少なくりますね(笑)。
さまざまな見積スタイルを理解し、適切に使い分けられることは、フリーランスにとって大きな武器だと思います。
クライアントや案件に応じて最適な見積が出せるようになると、信頼度も上がり、単価アップや継続依頼にもつながっていきますよ。
“予算ベース”で考えるという選択肢もある
わたし自身、いまは見積を出すときは「パッケージ価格で対応」が多いのですが、「予算内で最適な提案をする」パターンもあります。
たとえば、5万円ならテンプレート活用で効率重視、30万円ならデザイン提案や細部まで丁寧に作り込む、といったように、金額に応じた“価値の出し方”を変えるイメージです。
クライアントにも金額の根拠を説明しやすく、こちらもムダなくリソース配分ができるのがメリット。お互いにとって気持ちのいい進め方ができるんですよね。
ただし注意したいのが、買い叩きと紙一重になりがちな点。とくに初めてのクライアント相手では、対応範囲や条件をあらかじめ明確に伝えておくことが大事です。そこを曖昧にすると、あとからトラブルになる可能性もあるので要注意です。

見積提案がなかなか通らない…そんなときの一手はコレ!
何度か見積を出しても、「この仕様ならいくらになりますか?」「条件を変えたらどれくらい金額変わりますか?」「この部分をオプションにすると本体価格はいくらになりますか?」といったやり取りが続いて、なかなか話がまとまらない…。そんなケース、ありませんか?
経験上、この質問が出るときって、ほぼ「その見積ちょっと高いです」って遠回しに言ってる場合が多いんですよね。さらに、いろいろ提案しても、最終的に「今回は見送ります」と言われることもあり、こちらとしては出した労力が無駄になってしまうことも。
そんな時は、早い段階で「ご予算ってどれくらいですか?」とズバッと聞いてしまうのも手です。そして、その金額に合わせて、松・竹・梅のようなプラン提案をすると、話がスムーズに進みやすくなります。
予算に寄り添いつつ、こちらの主導権も保つ。そんなバランス感覚も、フリーランスには大切です。
「見積金額が高いと思われるかも…」そんな不安はないですか?
「この金額を提示したら高く感じられないかな…」
「他の安い人に流れるんじゃ…」
そんなふうに、見積を出すのが怖くなることってありませんか?
でも実際は、しっかりした根拠があれば、お客さんはその価格でちゃんと納得してくれます。
逆に、値引きを当たり前のように求めてきたり、最初から「全部コミで安くしてよ」と詰めてくるようなクライアントは要注意なんです。そういう案件って、あとからどんどん要求が増えるなど、自分だけが辛くなることがほとんどです。
自分を守るためにも、「安くする」より「価値を伝える」ことを意識していきましょう!
【まとめ】
繰り返しになりますが、制作費の決め方に正解はありません。案件の内容やクライアントのタイプ、自分のスキルや実績によっても、見積の出し方は変わります。
- 見積のパターンを理解しておくこと
- 追加対応・仕様変更に備えて適切な見積を出すようにすること
- 経験を重ねて、自分なりの感覚を育てていくこと
- クライアントの予算を最初に聞いてしまうのも有効
- しっかりとした価格の根拠があれば、高い安いの心配は必要なし
周りの相場に合わせたり、なんとなく感覚で見積を出したりすることが必ずしも間違いというわけではありません。…が、根拠のない価格設定は、クライアントに説明しづらく、トラブル時に自分が困る原因にもなります。
とくにフリーランスの場合、価格=信頼の基準にもなるため、説得力のある見積を出せるかどうかが大切なポイントです。
最初は迷いや不安があって当然ですが、いろいろな見積方法を実際に試していくことで、自分に合った判断基準や価格感覚が少しずつ身についてきます。
・・・
今回ご紹介した3つの見積スタイルをベースに、ぜひあなた自身の「価格設定スタイル」を磨いていってくださいね🤗